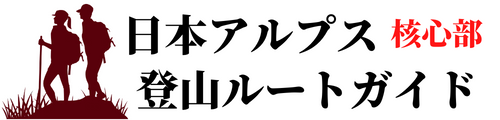甲斐駒ヶ岳とは
標高2,970mの甲斐駒ケ岳は、山梨県北杜市と長野県上伊那郡の県境に位置し、赤石山脈(南アルプス)のほぼ北端にあり日本百名山の一つです。 全般になだらかな南アルプスの中にあって、数少ない急峻な山容を呈しています。
頂上付近は白く輝く花崗岩が露出して、特に南側から見る山頂部は夏でも雪と見まごう様は大変印象的です。
駒ヶ岳と名が付く山は日本に18座ありますが、甲斐駒ケ岳はその最高峰です。数ある駒ケ岳の中でも筆頭と呼ぶにふさわしい高峰です。

北沢峠を登山口とする2ルートは大変アクセスが良く、駒津峰から分岐する直登りルートも難易度は低く登山初心者でもOKです。
一方、黒戸尾根を登るルートは、5合目以上から高度感のある梯子や鎖場が連続するスリリングなルートと言えます。
- 1. 甲斐駒ヶ岳の地図
- 2. 甲斐駒ヶ岳の山小屋
- 3. 甲斐駒ヶ岳のアクセス
- 4. 甲斐駒ヶ岳の登山コース概要
- 4.1. ① 北沢峠から双児山経由で直登りルート
- 4.2. ② 北沢峠から仙水峠経由で巻き道ルート
- 4.3. ③ 黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳ルート
- 5. 甲斐駒ヶ岳の日帰り登山は出来る?
- 6. 南アルプス林道バス発着所横の仙流荘に泊まる
- 7. 甲斐駒ヶ岳の登山口近くの温泉
- 8. 甲斐駒ヶ岳の天気の特徴
- 9. 甲斐駒ヶ岳の魅力
- 10. 甲斐駒ヶ岳の高山植物
- 10.1.1. 花崗岩で出来た甲斐駒ヶ岳では高山植物が育ちにくい
- 11. 甲斐駒ヶ岳の地質
- 12. 各種情報
- 12.1.1. 甲斐駒ヶ岳登山ツアー
- 12.1.2. 観光協会
- 12.1.3. 登山届提出
- 12.1.4. 登山地図のスマホアプリ
- 13. 甲斐駒ヶ岳山頂周辺の気温
- 14. 甲斐駒ヶ岳へ登るための装備と服装
- 15. 服装や装備品のチェックリスト
- 16. 甲斐駒ヶ岳に縄文人が登っていた?
- 17. 甲斐駒ヶ岳開山の歴史
- 17.1. 黒戸尾根登山道に多数の霊神碑や祠
- 18. 小尾権三郎の死の謎
甲斐駒ヶ岳の地図
- 甲斐駒ヶ岳|登山・トレッキングツアー
- 甲斐駒ヶ岳の登山地図(昭文社)Amazonで見る
- 甲斐駒ヶ岳の登山地図(昭文社)楽天で見る
甲斐駒ヶ岳の山小屋
甲斐駒ヶ岳のアクセス
甲斐駒ヶ岳の登山コース概要
① 北沢峠から双児山経由で直登りルート

アクセス
北沢峠 へのアクセスは長野県伊那市の仙流荘前から南アルプス林道バスに乗り約55分、または、山梨県南アルプス市の市営芦安駐車場前からバス又は乗合タクシーを使い広河原へ約1時間、そして広河原で北沢峠行きバスに乗り換え25分です。
コースタイム
- 登山:北沢峠→駒津峰 2時間50分 駒津峰→甲斐駒ヶ岳 1時間10分 合計:4時間
- 下山:甲斐駒ヶ岳→駒津峰 50分 駒津峰→北沢峠 1時間50分 合計:2時間40分
難易度 2/10
体力 2/10 (日帰り)
② 北沢峠から仙水峠経由で巻き道ルート

コースタイム
- 登山:北沢峠→駒津峰 2時間50分 駒津峰→甲斐駒ヶ岳 1時間50分 合計:4時間40分
- 下山:甲斐駒ヶ岳→駒津峰 1時間20分 駒津峰→北沢峠 2時間5分 合計:3時間25分
難易度 1/10
体力 3/10 (日帰り)
③ 黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳ルート

コースタイム
- 登山:竹宇駒ヶ岳神社→甲斐駒ヶ岳 9時間30分
- 下山:甲斐駒ヶ岳→竹宇駒ヶ岳神社 5時間40分
難易度 5/10
体力 3/10 (1泊)
甲斐駒ヶ岳の日帰り登山は出来る?
甲斐駒ケ岳への最短のアプローチは北沢峠を登山口とするルートです。長野県側、山梨県側からともにバス便があり、長野県側からは戸台口の仙流荘前から北沢峠行きバスが出ています。
山梨県側からは芦安からバスで広河原へ入り、広河原で北沢峠行きバスに乗り換えます。
また、JR身延駅からは奈良田を経由するバスで広河原へ入り、広河原で北沢峠行きバスに乗り換える事も可能です。
仙流荘前発のバスが最も早く北沢峠に着けます。また、シーズン期間中の各バスは、登山者の数に応じて臨時バスも増発されています。
しかし、北沢峠と甲斐駒ケ岳をピストンするコースタイムは7時間程なので日帰り可能な時間ですが、帰りのバスの時間を考慮すると、北沢峠辺りの山小屋に泊まる必要があり、実質山中一泊の行程となります。ただし、始発のバスに乗れば日帰り可能です。
南アルプス林道バス発着所横の仙流荘に泊まる

仙流荘
外来入浴料金; 大人(中学生以上) 600円
外来入浴時間 12;00~20;00 (受付終了19:30)
男風呂・女風呂共に露天風呂・内湯が1箇所ずつそれぞれにサウナ有り。
南アルプス林道バスの発着場まで徒歩1分です。
甲斐駒ヶ岳の登山口近くの温泉

尾白の湯 「べるが」
日帰り入浴施設の尾白の湯 「べるが」は超高濃度のミネラルが含有した天然温泉です。併設するキャンプ、宿泊施設が充実しています。
黒戸尾根登山口近くにあります。
【住 所】 〒408-0315 山梨県北杜市白州町白須8077-1
【T E L】 0551-35-2800
【営業時間】10:00〜20:00(最終受付19:30)。
【定 休 日】 水曜日
日帰り入浴料金
一人 830円(北杜市外) 420円(北杜市内)
甲斐駒ヶ岳の天気の特徴
甲斐駒ヶ岳の魅力




JR中央線の「特急あずさ」に乗り甲府盆地を過ぎた辺りで左手方向に鳳凰三山が現れ、その稜線の後方に山頂部だけをのぞかせる北岳が見えてきます。やがて右手方向に八ケ岳が大きくなってくると、左手の車窓から甲斐駒ケ岳が見え始めます。
中央線の日野春・長坂駅辺りから見る姿が最も美しく、摩利支天の岩壁を従えた山容はいっそう峻嶮に見え、登頂意欲を掻き立てられます。
これが小淵沢駅まで来ると摩利支天は見えなくなり、ただの三角形状のピラミッドの様な形となってしまいます。
JR中央本線長坂駅から歩いて10分ほどの所にある長坂池(牛池)からや北杜市神田の大イトザクラと甲斐駒ヶ岳とのコラボは一見の価値があります。
また、北杜市武川町の実相寺の桜と水仙が甲斐駒ヶ岳に花を添えます。境内には樹齢1800年~2000年の山高神代桜があります。
甲斐駒ヶ岳の高山植物







花崗岩で出来た甲斐駒ヶ岳では高山植物が育ちにくい
南アルプスにおいて花崗岩は甲斐駒ヶ岳から鳳凰三山にかけて分布しています。花崗岩は風化すると小さな粒状になり、雨によって流されてしまいます。
そのため甲斐駒ヶ岳では高山植物が育ちにくく、北岳、悪沢岳、赤石岳などに見られるような広範囲に渡る高山植物のお花畑を形成することがありません。
甲斐駒ヶ岳は花崗岩によって出来ています。花崗岩は、地下深くの溶岩がゆっくりと冷えて固まった岩石で、白と黒の鉱物結晶で、大きな岩体となります。
均一な構造を持っているため、固く割れ目が生じにくいのが特徴です。
そのため、建築用の石材として利用価値が高いものです。とわいえ、甲斐駒ヶ岳の山頂の様に急な斜面で、岩肌がむき出しになると、雨風によって僅かな割れ目が生じます。
すると細かい砂粒になって岩肌から剥がれ落ちるように風化していきます。この砂を真砂(まさ)と呼び、非常に流れやすいものです。
そのため、甲斐駒ヶ岳の山腹では高山植物があまり育たず、北岳の様な大きなお花畑を作ることはありません。
甲斐駒ヶ岳の地質


黒戸尾根がアサヨ峰の下部辺りから右手上方に伸び、黒戸山から少し下り、甲斐駒ケ岳山頂に突き上げています。深く浸食された地形は、数多くのバリエーションルートを提供し、尾白川、大武川の渓谷をはじめ、赤石沢奥壁、黄蓮谷などの岩登りのゲレンデとなっています。
日本列島を分断する地溝帯フォッサマグナが甲斐駒ケ岳の北側を走っています。この断層が山麓との標高差2200メートルを超える切り立った地形を作り出しています。山全体が花崗岩で作られ、山に降った雨が花崗岩によってろ過され、麓の白州町の扇状地に湧き出す水が名水として利用されています。
国道20号線沿いの「白州道の駅」では無料で名水を汲む事が出来る施設があります。また、サントリー工場で作られる「南アルプスの天然水」は有名です。
各種情報
甲斐駒ヶ岳登山ツアー
- 甲斐駒ヶ岳|登山・トレッキングツアー
観光協会
登山届提出
- 山梨県側は山梨県警察。電子申請やFAXなどで対応。
- 長野県は長野県県庁のホームページ
登山地図のスマホアプリ
- 山と高原地図のスマホアプリ
昭文社から販売されています。山と高原地図ホーダイ - 登山地図ナビアプリ 定額(500円/月 or 4800円/年)で61エリアの「山と高原地図」が使い放題。山と高原地図[地図単品購入版]地図1エリア 650円。
甲斐駒ヶ岳山頂周辺の気温
| 最高気温 | 平均気温 | 最低気温 | |
| 1月 | -9.1 | -14.8 | -20.5 |
| 2月 | -7.6 | -13.7 | -19.8 |
| 3月 | -3.3 | -9.9 | -16.0 |
| 4月 | 3.4 | -3.7 | -10.6 |
| 5月 | 8.1 | 2.1 | -4.2 |
| 6月 | 11.1 | 5.5 | 0.8 |
| 7月 | 14.3 | 9.0 | 4.8 |
| 8月 | 15.8 | 9.7 | 5.3 |
| 9月 | 11.5 | 5.8 | 1.3 |
| 10月 | 5.7 | -0.6 | -6.0 |
| 11月 | -0.4 | -7.0 | -12.8 |
| 12月 | -6.1 | -12.1 | -17.4 |
甲斐駒ヶ岳へ登るための装備と服装
| 軽アイゼン | 12本歯アイゼン | ピッケル | サングラス | テント | |
| 1月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5月 | × | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 6月 | ○ | × | × | △ | × |
| 7月 | × | × | × | △ | × |
| 8月 | × | × | × | △ | × |
| 9月 | × | × | × | △ | × |
| 10月 | × | × | × | △ | × |
| 11月 | × | × | △ | △ | ◎ |
| 12月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
服装や装備品のチェックリスト
| 登山地図 | 必須 登山地図を忘れると道迷いの原因に!甲斐駒ヶ岳はいたるところに分岐があります。 登山地図を持って行かないのは命取りと言えます。 |
| レインウェア | 必須 山の天候は急変します。天気予報で晴が出ていても レインウェアは必須です。また、防寒着としても使えます。 セパレートタイプの通気性と防水性を兼ね備えたゴアテックスがベストです。 |
| 帽子 | 必須 稜線に上がると直射日光が強烈に降り注ぎます。駒津峰辺りで森林限界を超えます。日よけ用のつばが広く軽いものをお奨めします。寒さが厳しいときは、耳を覆うニット製、冬山ではフルフェイスタイプをお奨めします。 |
| 日焼け止め | 必須 甲斐駒ヶ岳は3000メートル近くあるので、 稜線では日光を遮る木々が一切ありません。森林限界を超えると紫外線が強いので必帯です。 |
| 飲料水 | 必須 水不足にならないように天気の良い日は少し多めに持って行きましょう。 登山口の北沢峠から30分ほどの所にある仙水小屋にしか水場がありません。 登山行程に合わせて水の量を調整するとよいでしょう。 |
| ヘッドランプ | 必須 就寝後、完全に電気を落とす山小屋がほとんどです。真っ暗の中でトイレに行くのが困難な事もあります。また夜の行動を余儀なくされた場合にはライトがなければ歩けません。また、暗い内から山頂まで登り、御来光を拝むためにも必要です。 |
| 行動食 | 必須 登山のコースタイムが長いので多めに持っていくと良いでしょう。パン・ナッツ類・野菜ジュース、飲むヨーグルトなど立ち休憩で食べられるものがお薦めです。 |
| パックカバー | 必須 ザックが濡れないようにするためのザックカバーは雨に日には絶対必要です。ザックカバーも雨衣と同様に防水性が衰えてきます。 時折、防水スプレーをするなどのメンテナンスが必要です。 |
| 救急薬品 | 必須 切り傷、擦り傷にカットバン、絆創膏を持っていくと良いでしょう。虫刺され薬品も。仙丈ヶ岳も連続で登る場合には、登山行程が長く体力を必要とするので、トクホンのような筋肉痛に効く貼り薬。 |
| ティッシュペーパー | 必須 登山中いきなりしたくなってしまった場合や、転んで出血した時の止血用として必帯です。ポケットティッシュを水で濡らし耳栓として使う場合にも有効です。 |
| 防寒着 | 必須 薄手のフリース,セーター、軽いダウンジャケット。 甲斐駒ヶ岳山頂では、7~8月でも最低気温が5度近くまで下がることがあります。軽くて保温性の高いものを選びます。ゴアテックスのレインウェアを その上に着ると更に保温性が高まります。 |
| 手袋 | 必須 黒戸尾根を登る時には鎖場や梯子が連続します。三点支持で登る時に使います。革製の手袋がベストですが、軍手でもOKです。 |
| 耳栓 | あったら良い 甲斐駒ヶ岳は山中の山小屋で最低でも一泊するコースがほとんどです。山小屋では大部屋が基本です。就寝時に いびきをかく人が必ずいます。耳栓の効果は絶大です。 |
| カメラ | あったら良い 大展望の景色をおさめて山旅の思い出にぜひどうぞ。ウエストポーチに収納出来る大きさであることが望ましいです。 |
| ビニール袋 | あったら良い ごみ入れとして、使用前の下着入れ、使用後の下着入れとして7~8個あると便利です。 |
| 保険証(コピー) | あったら良い 事故や遭難時に必要です。 |
| サブザック | あったら良い 黒戸尾根ルートの場合、七丈小屋にザックを置いて、サブザックで身軽な状態で登頂出来ます。水、カッパなど必要最低限が入る軽いコンパクトなものを使用すること。 |
| シュラフカバー | あったら良い 遭難時や混雑している山小屋(一つの布団に2人)で役に立ちます。毛布2枚を床に敷きゴアテックス製のシュラフカバーに入ります。 |
甲斐駒ヶ岳に縄文人が登っていた?

甲斐駒ケ岳は、江戸時代後期文化13年(西暦1816年)6月に、小尾権三郎が黒戸尾根からの初登頂に成功します。それ以後、山岳信仰の霊場として隆盛をきわめることになります。
しかし、驚くことに1988年に信藤祐仁氏らは、甲斐駒ケ岳山頂に1等三角点を設置する工事の際に、縄文時代後期の無紋土器を偶然見つけます。
これは日本で一番高い所で発見された縄文土器ですが、近年に登山者が故意に埋めたものかは確定されていません。
もし、縄文人達が山頂まで登ったとするならば、どうやって登ったのであろうか?数千年の時を経て、縄文人達の山岳信仰が息づいているのを覚えます。
甲斐駒ヶ岳開山の歴史
黒戸尾根登山道に多数の霊神碑や祠





江戸時代の初期には既に開山されていたようだが、はっきりした事はわからず、
明確な資料が残るのは江戸時代後期文化13年(西暦1816年)6月のことです。開山を行ったのは長野県茅野市生まれの修験道の行者である延命行者・鐇弘法印、俗名・小尾権三郎です。
小尾権三郎は、文化10年十八歳の時に、山梨県北杜市白州町横手の名主であった山田家に甲斐駒ケ岳開山の申請を出します。当時、不浄の者が山に入ると洪水など自然災害などが起こると考えられ、修行が不十分な権三郎には入山の許可がおりませんでした。権三郎は、甲斐駒ケ岳を源流とする尾白川渓谷を中心として、日本全国の霊山で修行を積み、3年後の22歳になった時、再び山田家に甲斐駒ケ岳開山の申請をします。山田家では権三郎の修行に多くの支援をしていたようで、山田家の一角の小さな小屋を権三郎の修行部屋として貸していたと言います。
文化13年、権三郎22歳の時に甲斐駒ケ岳開山の許可がおります。そして、権三郎は、甲斐駒ケ岳に入り、開山に挑みます。しばらく経っても権三郎が戻らないので、信州諏訪の実家では心配になり、捜索も行われた様です。入山から3ヶ月経ってヒゲモジャの行者が山から降りてくる姿を見たという言い伝えが山田家に残っています。※権三郎がどのルートを通って開山したかは不明です。
開山に成功した権三郎は、京に上って、「神道神祇管長白河殿」より「駒ケ嶽開闢延命行者五行菩薩」という尊称を賜ることになりますが、開山から3年後に若くして亡くなります。甲斐駒ケ岳の開山の功績を称えて黒戸尾根六合目にある不動岩に「大開山威力大聖不動明王」として祀られたとされています。その後、甲斐駒ケ岳は山岳霊場として信仰登山が盛んになっていきます。
黒戸尾根の登山道には多数の石碑・霊神碑が建立されています。 駒ヶ岳講は江戸時代後期から盛んになり、出発前には精進潔斎を行い白装束に身を包み登拝しました。講のリーダーを先達(せんだつ)と呼び、経験及び知識豊富な人がなったようです。先達が死ぬと魂は山に帰るとされ、霊神碑を山道に建立し、依代として祀ったとされています。
尾白川渓谷近くの竹宇と横手の駒ヶ嶽神社は、山頂を本宮(奥宮)とする前宮(里宮)です。竹宇駒ヶ嶽神社では4月10日から16日の間の日曜日に、横手駒ヶ嶽神社では4月20日に祭典が催され、太々神楽が奉納されます。当日は、多くの氏子、崇敬者、講社などの参拝者で賑わいます。
※竹宇駒ヶ嶽神社と横手駒ヶ嶽神社とは関係がなく、駒ヶ岳講も別々に組織されています。
※ 精進潔斎(しょうじんけっさい)-肉・魚の類を口にせず,飲酒・性行為などを避け,おこないを慎むことによって,心身を清浄な状態におくこと。
※ 講-同一の信仰を持つ人々によるグループである。
※ 依代(よりしろ)-神霊が降臨する際の媒体となるもの。
小尾権三郎の死の謎
権三郎は25歳という若さで亡くなっています。
死の原因は不明ですが、諏訪地方に多くいた御嶽山信仰の道者との間に何かのトラブルを抱えていたのかもしれません。
権三郎は、甲斐駒ケ岳開山後、錫杖の頭や巻物など修験者として必要な9品を山田家に渡すよう権三郎の父、今右衛門に頼みます。このことは権三郎が今後修験者として生きていかない決意を意味しています。 これらの9品は、権三郎の死後13回忌に山田家に届けられています。
彼の出身は長野県茅野市上古田(村岡平)で、諏訪地方における修験道の中心が御嶽山であったことから、甲斐駒ケ岳における修験道を広めるのは容易なことではなかったようです。その辺に死の原因が隠されているかもしれません。